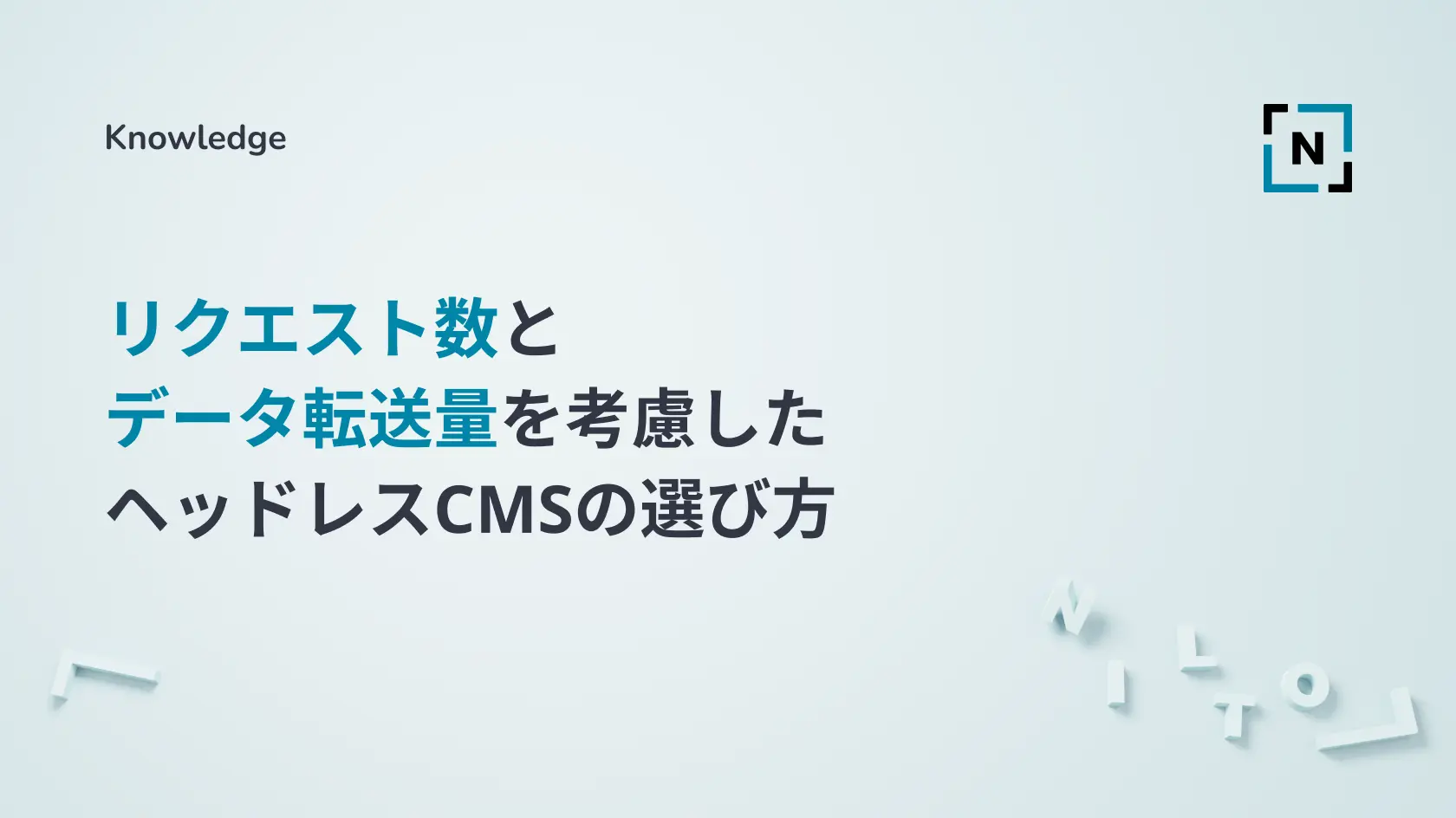目次
多くのクラウド型CMSで、利用規模に応じた料金体系が採用されています。その指標となるリクエスト数とデータ転送量について理解し、ユースケースに応じたコストパフォーマンスの高いCMSを選定しましょう。
クラウド型CMSにおける利用量制限の概要
クラウド型CMSでは、料金プランごとに月間利用量の上限が定められています。利用量を超過した場合、超過料金もしくは利用制限が発生する仕組みになっています。翌月になると利用量のカウントはリセットされ、また上限まで利用することができます。利用量の指標としてリクエスト数やデータ転送量が採用されています。ここではそれらの基本概念について説明します。
CMSをCMS事業者が運用するクラウド上で利用する形態をクラウド型(SaaS型)CMSと呼びます。
CMSをユーザーが用意したサーバーやIaaS/PaaSにインストールして利用する形態をインストール型CMSと呼びます。
リクエスト数とは
クラウド型CMSにおけるリクエスト数とは、CMSにアップロードした画像や動画といったメディアファイルへのアクセスおよびCMSが提供するAPIへのアクセスの累積回数を指します。
メディアファイルへのリクエスト数とAPIへのリクエスト数のそれぞれもしくは一方だけに上限を設けて制限するケースもあれば、それらを合算した数字で上限を設けて制限するケースもあります。
なおNILTOはメディアファイルのリクエスト数とAPIのリクエスト数を合算した数字で上限を設けています。
データ転送量とは
クラウド型CMSにおけるデータ転送量とは、CMSにアップロードした画像などのメディアファイルやAPIにアクセスされることで転送されたデータサイズの累積値を指します。アップロードとダウンロードの両方がデータ転送量に該当しますが、クラウド型ヘッドレスCMSにおいてはダウンロードのみを対象に制限されることがほとんどですので、ここでは説明簡略化のためダウンロードのみ制限されることを前提にします。
メディアファイルのデータ転送サイズとAPIレスポンスのデータ転送サイズのそれぞれもしくは一方だけに上限を設けて制限するケースもあれば、それらを合算した数字で上限を設けて制限するケースもあります。
なおNILTOはデータ転送量に制限を設けていません。
リクエスト数とデータ転送量の関係
リクエスト数とデータ転送量は正の相関関係にあります。メディアファイル1つあたりの平均サイズやAPIから返却されるレスポンスデータの平均サイズが大きければ大きいほど、リクエスト数に対してデータ転送量が大きくなり、逆に平均サイズが小さければ小さいほど、リクエスト数に対してデータ転送量は小さくなります。
PVとリクエスト数・データ転送量の関係
PV(ページビュー・ウェブページの表示回数)とリクエスト数・データ転送量は密接に関係しています。
一般的な実運用において、CMSのリクエスト数とデータ転送量の発生原因のほとんどはPVによるものです。それ以外の要因はボリューム的に無視しても問題ありません。
想定される月間PVからリクエスト数とデータ転送量を見積もることができます。
例えば平均的に1つのウェブページにCMSから取得する画像が4枚入っていて、1画像あたり平均500KBだとすると、1PVあたりリクエスト数はAPI1回+画像4回=5回となり、1PVあたりデータ転送量は画像500KB×4=2MBとなります。なお1PVあたりAPIリクエストが1回というのは、採用するアーキテクチャやページの複雑さによって変わります。またデータ転送量にAPIのレスポンスサイズを含めていないのは、それが画像サイズと比較して無視できるほど小さいからです。
利用量の上限に達した場合
リクエスト数やデータ転送量の上限は月ごとに設定されます。月の途中で上限に達した場合、利用制限もしくは超過料金が発生します。どちらになるかは契約している料金プランによって異なります。
利用制限が発生するプランの場合、利用量の上限に達した時点でメディアファイルへのアクセスやAPIへのアクセス、入稿画面へのアクセスなどに制限が発生します。通常運用できなくなり、CMSを組み込んでいるウェブサイトが表示できなくなるなどの影響が発生する場合もあります。超過料金は基本的に発生しません。
翌月になると利用量のカウントはリセットされ利用制限は解除されます。また利用量の上限までは通常運用できます。
超過料金が発生するプランの場合、利用量を超過しても利用自体には制限がかからず、CMSおよびCMSを組み込んだウェブサイトの運用に影響はありません。月ごとに超過した利用量を集計し、それに基づく超過料金を精算します。
CMS事業者から見た利用量制限の必要性
クラウド型CMSの場合、CMSのインフラコストはCMS事業者が負担します。クラウド型CMSを含む現代のクラウドサービスのほとんどはIaaS/PaaS上で構築されており、その場合、利用量に応じたインフラコスト負担が事業者に発生します。エンドユーザーによる利用が増えれば増えるほど、CMS事業者にかかるコストも増える構造となっています。
CMS事業者からすると、原価割れを起こさず採算を合わせるためには、利用量に応じた料金体系としなければなりません。そのためにCMS事業者は利用量に上限を設け、それを超える場合は利用制限もしくは超過料金が発生する料金プランを提供しています。
インストール型CMSでの利用量制限
インストール型CMSではクラウド型CMSとは異なり、CMSのインフラコストをCMS事業者ではなくユーザーが負担します。CMS事業者はインフラコストを負担しないことから、利用量を制限する必要がありません。そのため利用量を制限しないライセンスであることがほとんどです。
ユーザーとしてはインフラを設計・運用するコストがかかりますが、ユースケースに合わせて最適なインフラを構築することができれば、全体的にコストを圧縮できる可能性があります。
画像最適化機能でデータ転送量の削減
CMSによっては画像最適化機能が備わっています。画像最適化機能とは、CMSにアップロードされた画像ファイルがウェブページで表示される際に、アップロードされたまま表示するのではなく、縦横サイズや画質、フォーマットなどを表示場所ごとに適した形に変換してから表示する機能です。これを活用することで、画像が実際に転送されるデータサイズを削減することが可能です。それによりデータ転送量を節約することができます。
利用量を考慮したCMS・料金プラン選定のポイント
どのようなウェブサイトを実現したいかによってコストパフォーマンスの良いCMSや料金プランは異なります。ここではCMSを選定する際に利用量に関して考慮すべき観点を紹介します。
PVベースで利用量を見積もる
CMSを導入するウェブサイトが目標としている月間PVから、リクエスト数とデータ転送量を見積もりましょう。それをCMSの料金プランと照らし合わせることで、利用量に関して発生する費用を試算することができます。
基本料金と超過料金単価
多くのクラウド型CMSは、基本料金+超過料金という料金体系を採用しています。基本料金に含まれる利用量の上限に収まるかどうか、超える分については超過料金単価をかけた費用が発生するので、それが妥当かどうかを確認しましょう。
突発的なアクセス急増を想定する
ウェブサイトを運用していると、突発的にアクセスが急増することがあります。その場合にどの程度の費用が発生しうるかを想定しましょう。
超過時の挙動
リクエスト数もしくはデータ転送量を超過した際に、利用制限が発生(=超過料金なし)するのか、超過料金が発生(=利用制限なし)するのかを確認しましょう。
業務利用であれば、運用が止まるのは問題があるため、超過料金が発生してでも利用制限が発生しないほうが望ましいと考えられます。
一方でプライベートな業務外利用であれば、突発的なアクセス急増で高額な超過料金を請求されるのは困るため、利用制限が発生しても超過料金が発生しないほうが望ましい場合があります。
リクエスト数もしくはデータ転送量が無制限
クラウド型CMSは、リクエスト数もしくはデータ転送量のどちらかが無制限になっていることがあります。
ウェブサイトで表示したい画像や動画などメディアファイルの1つあたり平均サイズが大きければ大きいほど、データ転送量無制限(リクエスト数のみ制限)が適しており、逆に平均サイズが小さければ小さいほどリクエスト数無制限(データ転送量のみ制限)が適しています。
NILTOが有利なケース・不利なケース
利用量に関して、NILTOを選ぶと有利なケース・不利なケースを紹介します。
NILTOが有利なケース
NILTOはリクエスト数に上限を設け、データ転送量は無制限という料金体系を採用しています。そのため画像や動画などメディアファイル1つあたりの平均サイズが大きければ大きいほど有利になります。
高解像度な画像や動画ファイルをCMSにアップロードして多用したい場合は、他のCMSよりコストパフォーマンスが高い可能性があります。
NILTOが不利なケース
上記とは逆に、動画を使わず小さな画像ファイルが多い場合など、メディアファイル1つあたりの平均サイズが小さければ小さいほど、他のCMSよりコストパフォーマンスが悪くなる可能性があります。
貴社に最適なプランをご提案します
NILTOは貴社のニーズに合わせて料金プランを柔軟にカスタマイズできます。
想定される利用ボリュームに応じて費用対効果の高いプランをご提案します。
お見積りのご依頼やご不明な点は、以下からお気軽にお問い合わせください。